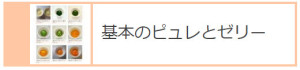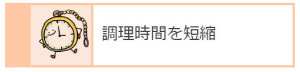やわらかい・飲み込みやすい
食べやすい食品の形状
食べる人の「噛む・飲み込むチカラ」によって食べやすい食品の形状は違います。
私は下表のように色分けしたA~Fの6つのグループに分けて考えています。
表の見方
表の上部・左端にある「噛む力」「飲み込む力」の欄を見て、食べる人がA~Fのどこ
に当たるかを食事の様子からご判断します。
例えば、「硬いものが噛みにくい」「ときどき飲み込みにくそうにしている」なら、
Bグループの「歯茎でつぶせる形状」が適しているとわかります。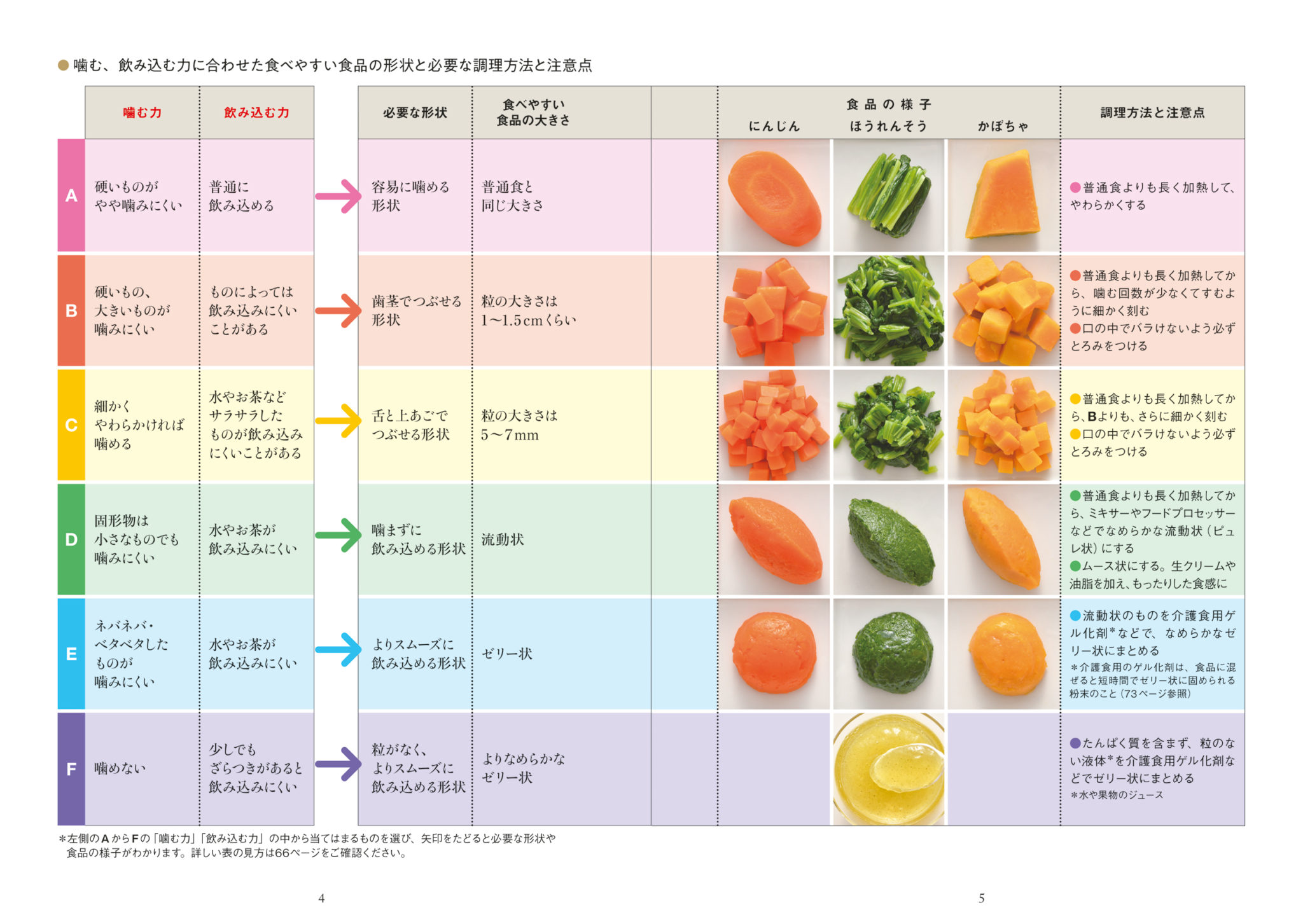
上の表も文字が読みにくい場合は、画像をクリックしてください。拡大画面になります。
ある程度、自分で噛める場合は
A・B・Cの3つのグループは、ある程度自分で噛めるひとのグループです。
この3つに当てはまる場合は、噛む回数が少なくてすむよう、素材を長めに加熱し
柔らかくし、細かくカットします。
Cグループの場合、食材を細かく刻むと、口の中でバラけやすくなり、かえって
誤嚥を招きやすくなります。片栗粉やとろみ調整剤などで必ずとろみを付けるように
しましょう。「とろみ剤」ページ(←リンク先)を参考になさってください。
固形物が噛みにくい、噛めない場合は
固形物が噛みにくい、あるいは噛めない場合はD・E・Fのグループになります。
こちらの場合はミキサーやフードプロセッサーを使います。
やわらかくゆでた食材に水分を加えてミキサーにかけると、粒のない、とろみのある
「ピュレ」ができます。
水分を少なめにすると「ピュレ」より濃度の濃い「ペースト状」に。
「ペースト状」に生クリームなどを加えると、よりもったりした「ムース状」となり
食感が変化します。
「ピュレ」を薄めてゼラチンなどで固めたものが「ゼリー」です。
加熱冷却することなく常温でゼリーになる「介護食用ゲル化剤」(←リンク先)
が便利です
クリコ流の特長のひとつは 「野菜のピュレ」とその活用にあり
繊維の多い野菜は噛みにくい、飲み込みにくい。栄養豊富な野菜をたくさん食べても
らうにはどうしたらいい?
そこで活用したいのが野菜のピュレです。
人参、かぼちゃ、ブロッコリー、ほうれん草、じゃがいも、玉ねぎ、キノコ類…。
それぞれ加熱してミキサーにかけて野菜ピュレにします。
ピュレに他の食材を組み合わせることで様々な野菜ピュレ料理(←リンク先)作ること
ができます。
小分け冷凍で調理時間を短縮できる
野菜ピュレをたくさん作って小分けに冷凍しておけば、必要な時にサササっと短時間で
調理でき、あと何かひと品ほしいという時も助かる!
様々な野菜ピュレの作り方は「基本の野菜ピュレ」(←リンク先)です。
飲み込むチカラを助けるゼリーも、野菜ピュレを材料に作ることができます。
ぜひぜひお役立てください。
◆「ピュレ」の作り方、活用法のページへ◆